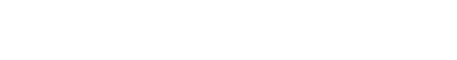2025/05/21 公開
夜泣きはいつから始まるのか睡眠リズムとの関係を知ろう
「赤ちゃんの夜泣きって、いつから始まるの?」
初めての育児で、夜中に何度も泣き出すお子様を前に、不安や疲れを感じているママやパパは少なくありません。理由がはっきりしないまま続く夜泣きに、どう向き合えばいいのか悩んでいる方も多いはずです。
この記事では、夜泣きが始まる時期や背景にある睡眠リズムの発達、日々の過ごし方でできる工夫、親御さん自身の負担を軽くする考え方まで、やさしく丁寧に解説しています。
夜泣きは一時的なもの。そう思えるようになるヒントを、ぜひここで見つけてみてください。
はじめに ~夜泣きに悩むママ・パパへ~
お子様の夜泣きに悩んだことはありませんか?夜中に突然大声で泣き出したり、寝かしつけたと思ったらすぐに目を覚まして泣いたり…。特に育児が初めての方にとっては、「これって普通なの?」「病気じゃないのかな?」と不安になる場面が多いものです。
日中は家事やお世話に追われ、やっと夜になって体を休められる…と思った矢先に始まる夜泣き。ママやパパが疲れを感じるのも無理はありません。特にお産用の体の疲れが回復しきっていない時期は、心身の負担が大きくなりがちです。
でも、夜泣きは「異常」な反応ではありません。実は、赤ちゃんの脳や体が元気に育っている証でもあります。とはいえ、毎晩続くと大変ですし、少しでも楽に乗り越えたいですよね。
夜泣きがいつから始まるのか、その理由や向き合い方を知ろうとしても、難しい説明ばかりで戸惑ってしまうかもしれません。ここでは、育児の現場で感じる悩みに寄り添いながら、できるだけ具体的でわかりやすい形でお話ししていきます。毎日の生活の中で「これならやってみようかな」と思える内容をお届けしていきます。
夜泣きってなに?どんなときに起きるの?
夜泣きとは、お子様が夜の睡眠中に突然目を覚まし、理由がはっきりしないまま泣き続ける状態を指します。お腹がすいている、体が暑い・寒い、おむつが気持ち悪いといった原因であれば、対処すればすぐに泣きやむことがよくあります。ただ、夜泣きの場合はそういった明確な理由が見つからない場合がほとんどです。
泣いているお子様を抱っこしてもなかなか落ち着かず、授乳してもすぐに泣き出す…そんな状況になると、親としてはどう対応したらよいのか困ってしまいますよね。
そもそも、夜泣きには医学的な明確な定義はありません。だからこそ、人によって捉え方や感じ方が異なります。ある人にとっては「夜中に1回泣いて起きるだけ」でも夜泣きと感じるかもしれませんし、ある人にとっては「何をしても2時間泣き続ける」ことが夜泣きだと思うかもしれません。
ただ共通して言えるのは、「赤ちゃんが夜に起きて泣き、その理由がはっきりしない状態」が続いているという点です。そして、それによって親御さんの睡眠も妨げられているため、家庭全体にとって大きなストレスの原因になりやすいのです。
夜泣きはいつから始まる?そのタイミングと理由
赤ちゃんの夜泣きが始まる時期については、個人差がとても大きいですが、一般的には生後5~6ヶ月ごろが多いとされています。
なぜこの時期なのでしょうか?その理由は、赤ちゃんの「体」と「脳」の発達が大きく関係しています。
生後5ヶ月を過ぎたころから、赤ちゃんは次のような変化を見せはじめます。
- 昼と夜の区別が少しずつついてくる
- まとまって眠る時間が増えてくる
- 感情がより豊かになり、表現も強くなる
- 視覚や聴覚などの感覚が発達して、周囲の刺激に敏感になる
こういった変化は成長の表れですが、それに伴い「浅い眠り」の時間が増え、少しの刺激でも目を覚ましやすくなります。眠っている間に音や光、体の違和感などに反応し、突然泣き出す場合もあります。
また、生後6〜9ヶ月ごろには「記憶力」や「感情表現」もぐんと伸びてきます。「ママと離れるのがさびしい」「知らない場所が怖い」といった気持ちが芽生えてくるため、日中の体験が夜の眠りに影響することも増えてきます。
たとえば、昼間にお母様と長時間離れていた日や、初めての場所で緊張した日などは、夜になって不安が強まり、赤ちゃんが泣いてしまう場合があります。
睡眠リズムってなに?なぜ関係があるの?
夜泣きと深く関わっているのが「睡眠リズム」です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、簡単に言えば「眠るタイミングと起きるタイミングの流れ」のことです。大人でも毎日夜10時ごろに眠くなって朝7時に自然と目が覚めるというリズムがありますよね。これが「体内時計」と呼ばれる働きです。
この体内時計は、朝に光を浴びたり、夜に暗い場所でリラックスしたりすると整っていきます。でも、赤ちゃんはこの体内時計がまだ整っていない状態で生まれてきます。だから、昼と夜の区別がつかず、1日の中で寝たり起きたりを繰り返しているんですね。
特に新生児のころは、1回に寝られる時間が短く、2〜3時間おきに目が覚めて泣きます。これは本能的なもので、空腹を伝えたり、不快を知らせたりする大切なサインです。
生後3〜4ヶ月を過ぎると、徐々に夜の睡眠が長くなりはじめます。体内時計が少しずつ整い、昼間は起きている時間が長く、夜は眠る時間が増えてくるのです。ただし、このリズムが完全に安定するまでは、何かの拍子にすぐに乱れてしまいます。
たとえば、昼寝の時間が長くなったり、夜寝る直前まで明るいテレビを見ていたり、大きな音に驚いたりすると、赤ちゃんの眠りのリズムはすぐに乱れやすくなります。
リズムが不安定なまま眠っていると、浅い眠りのタイミングでちょっとした刺激が加わるだけでも目を覚まし、泣き出す場合があります。こうした反応が、夜泣きにつながるのです。
どうして夜泣きするの?考えられるきっかけ
夜泣きには、いくつかのきっかけや背景が考えられます。見た目には理由が分かりづらくても、赤ちゃん自身は強い不快感や不安を抱えていて、泣かずにはいられない状態になっている場合があります。
たとえば、汗をかいて暑い、布団が重くて動きにくい、寒さで足先が冷えているなど、ほんの些細な不快感でも眠りを妨げやすくなります。大人なら自分で布団を調整してまた眠るような場面でも、赤ちゃんはうまく対処できないため、泣いて気持ちを伝えようとするのです。
また、歯が生え始める時期も夜泣きが多くなるタイミングです。歯茎のむずむずや痛みで夜中に何度も目を覚ますことがあります。とくに上下の前歯が生え始める生後6〜10ヶ月ごろは、夜泣きが一時的にひどくなるケースもあります。
夜泣きは、体の不快感や環境の変化だけでなく、お子様の「心の成長」とも深く関わっています。生後半年ごろを過ぎると、赤ちゃんの脳は「記憶」や「感情」を少しずつ扱えるようになってきます。この時期から、「こわい」「さびしい」「驚いた」といった感情を持ち、それを反応として表す力がついてきます。
まだ言葉で気持ちをうまく伝えられないため、感情を整理できないまま眠ってしまうと、夜中にふと目が覚めたときに不安が高まり、泣いてしまう場面があります。特に、人見知りが始まるころや、親と離れる時間が増えてきた時期には、こうした夜泣きが目立つようになります。
これは、お子様が「自分と他人の違い」に気づき、他者との関係を意識し始める過程でもあります。赤ちゃんが心の面でも大きく育っているサインと捉え、無理なく寄り添っていくことが大切です。
さらに、赤ちゃんも夢を見るといわれています。楽しい夢だけでなく、不安を感じるような夢を見る場合もあります。夢の内容はわかりませんが、突然泣き出してなかなか落ち着かない様子が見られるときは、夢の影響を受けている可能性も考えられます。
夜泣きはいつまで続く?終わる日はくるの?
「夜泣きっていつまで続くの?」と、毎晩の泣き声に疲れている親御さんにとって、この疑問はとても切実ですよね。
結論から言うと、夜泣きが続く期間にはかなりの個人差があります。あるお子様は数週間で落ち着きますし、あるお子様は2〜3歳ごろまで続くケースもあります。
多くの場合は、生後1歳半〜2歳くらいの間に自然と減っていきます。これは、お子様の脳の発達が進み、生活のリズムが安定し、言葉で気持ちを伝えられるようになってくるからです。
たとえば、それまでは「なんとなく不安」「お腹がすいたかも」「暑いかも」などの気持ちを泣くことでしか伝えられなかったお子様も、言葉を使えるようになると「ママ、お水」「寒い」「だっこして」といった形で具体的に伝えられるようになっていきます。
また、生活の中で「自分でできること」が増えていくと、自信がついて不安が減っていきます。それにともない、夜中に起きる回数も減り、眠りも深くなっていくのです。
とはいえ、成長の過程には波があり、一度おさまった夜泣きが再び始まる場合もあります。風邪をひいたときや保育園に通い始めたとき、下のきょうだいが生まれたときなど、環境や体調の変化によって一時的に夜泣きが再発する場面も見られます。
夜泣きが完全になくなるのは個人差があるものの、多くの場合、成長とともに自然と終わっていきます。「ずっと続くわけじゃない」と思えるだけでも、少し気持ちが軽くなりますよね。
夜泣きをやわらげるために今日からできること
夜泣きを完全になくすのは簡単ではありません。ただ、毎日の過ごし方や寝かしつけに少し工夫を加えるだけで、泣く頻度が減っていくケースは多く見られます。
たとえば、朝は決まった時間に起きる習慣をつけると、1日のリズムが整いやすくなります。目覚めたらすぐにカーテンを開けて自然の光を取り入れると、体が朝を感じ取りやすくなります。
昼間はしっかり体を動かす時間をつくると、夜の眠りが深くなりやすくなります。ベビーカーでのお散歩でも、室内での遊びでもかまいません。大切なのは、赤ちゃんが日中に活動し、疲れた状態で夜を迎えることです。
夕方から夜にかけては、だんだんと静かな環境に切り替えていきます。明るい照明やテレビの音は控えめにして、穏やかな雰囲気を心がけましょう。寝る直前に遊びすぎたり、テンションが上がってしまうと、眠りに入りにくくなってしまいます。
就寝前には、毎晩同じ流れを繰り返す「ねんねの儀式」を取り入れてみましょう。たとえば、入浴のあとに絵本を読み、子守唄を歌って寝かしつけるなど、いつも同じ順番で進めていくと、お子様の中に「これをしたらもう寝る時間なんだ」という感覚が生まれてきます。
小さな積み重ねでも続けていけば、少しずつ眠りのリズムが整い、夜中に泣く回数も減っていくはずです。
パパやママが休める環境づくりも大切
夜泣きは、お子様だけでなく育てている親御さんにとっても大きな負担になります。夜中に何度も起こされる日が続くと、体が休まらず、日中にぼーっとしたり、些細な出来事にイライラしてしまう場面も出てきます。
「自分がしっかりしなきゃ」と思えば思うほど、心にゆとりがなくなってしまうこともあるかもしれません。でも、育児は決して一人で抱える必要はありません。無理のない範囲で少しずつ手放していく工夫も大切です。
たとえば、日中に短い時間でも仮眠を取るようにしてみる。夫婦で交代して寝かしつけを担当する。実家や地域のサポートに頼ってみる。そういった工夫を取り入れるだけで、少し心と体が軽くなるかもしれません。
「夜泣きがつらい」と感じるのは、ごく自然な感情です。赤ちゃんのためにも、自分を責めず、無理のない範囲で少しずつ休める環境を整えていく意識が大切です。
ベビー用品レンタルの活用で夜泣き対策がラクに
夜泣きが続く時期に役立つアイテムを上手に取り入れると、寝かしつけが少しスムーズになることもあります。たとえば、心地よい揺れで赤ちゃんを落ち着かせる電動スイング、静かに音楽が流れるベビーベッド、眠りに導く優しいライトなどがあります。
こうした育児グッズは便利ですが、購入となると費用がかかりますし、使う期間も限られています。すぐに使わなくなる可能性があると、手を出しにくいと感じる方もいるでしょう。
そんなときは「レンタル」という方法を検討してみてもよいかもしれません。必要な時期だけ借りられるので、使わなくなった後の置き場所にも困りませんし、費用の面でもぐっと負担が減らせます。
赤ちゃんの成長にあわせて、必要な寝具やサポート器具も少しずつ変わっていきます。たとえば、生後3ヶ月までは小さなクーハンが適していて、6ヶ月を過ぎるころにはベビーベッドが使いやすくなります。レンタルを活用すれば、その時期に合ったアイテムへ柔軟に切り替えやすくなります。
さらに、赤ちゃんによって「これだとよく眠る」というものが違う場合もあります。レンタルでいくつか試してみることで、お子様にぴったり合うアイテムを見つけやすくなるというメリットもあります。
親御さんが少しでもラクに育児を続けられるように、無理なく取り入れられる手段の一つとして、ぜひレンタルも視野に入れてみてください。
おわりに
夜泣きが続くと、「いつになったら朝までぐっすり眠れる日が来るんだろう」と、毎晩ため息が出てしまう日もあるかもしれません。でも、これはお子様が順調に成長している証しでもあります。昼と夜の区別がわかるようになり、感情も豊かになってきて、夜中にふと目を覚ましたときに「こわい」「さびしい」と感じることがあります。そんな反応も、赤ちゃんが少しずつ世界を受け止める力を育てている証しです。
「夜泣きは成長の一部」と受け止められるようになると、心に少しゆとりが生まれるかもしれません。もちろん、毎晩続くとつらさは消えませんが、「いつか終わる」と思えるだけでも、前に進む力になります。
できるだけ生活リズムを整えて、お子様が安心して眠れる環境を用意してあげてください。そして、ママやパパ自身も、ひと息つける時間や、気持ちをゆるめられる手段を見つけてみてください。
夜泣きの時期が過ぎたとき、振り返って「がんばったね」と言える日がきっとやってきます。その日まで、少しずつ、一歩ずつ、一緒に歩んでいきましょう。